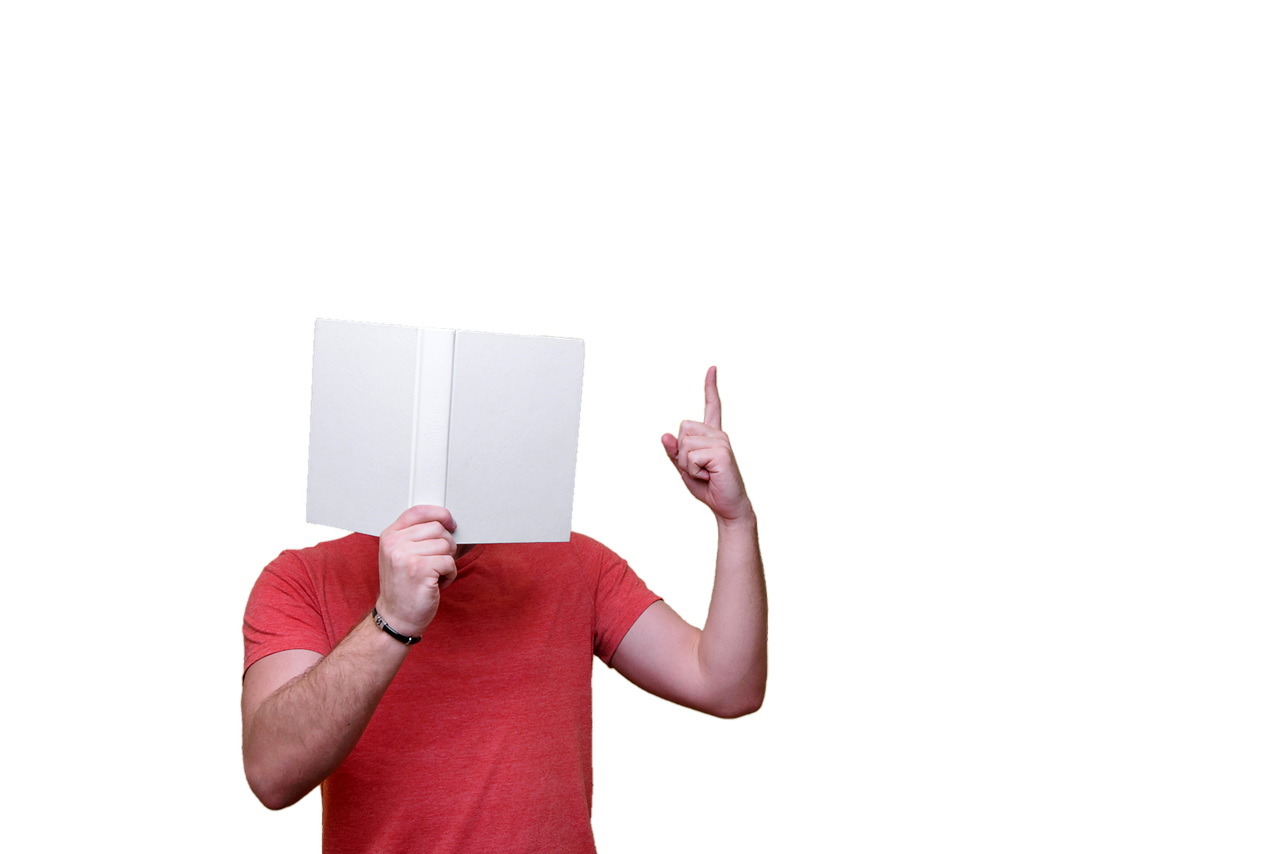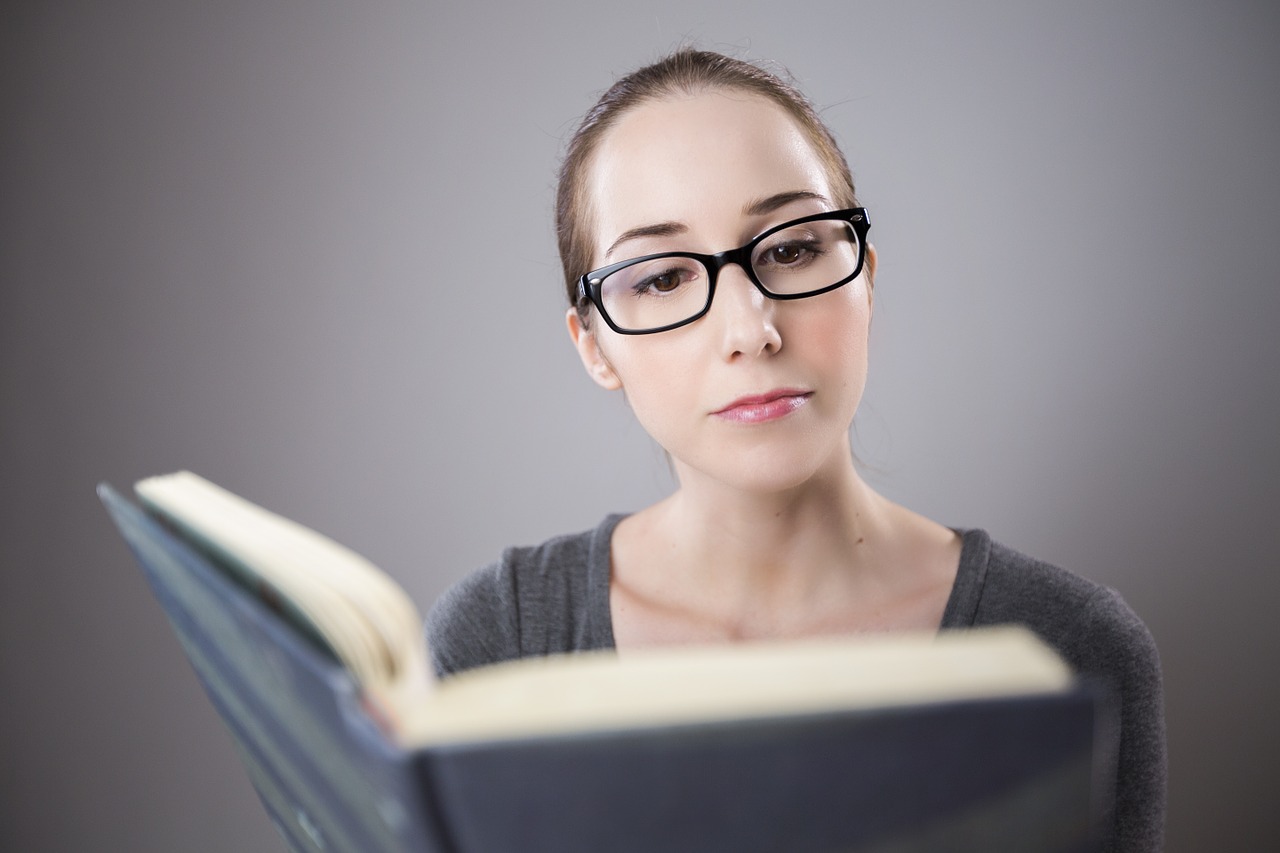1.様々な企業が取り組んでいる省エネ対策
環境事業に取り組む企業が増えており、いろいろな分野で自然に優しいエコな活動が行われています。
その中でも特に力を入れて行われているのが、化石燃料から脱却してクリーンエネルギーを普及させることです。
クリーンエネルギーの代表といえば太陽光発電ですが、膨大な敷地面積が必要という欠点もあるため、風力発電やバイオマス発電などに注目する企業も多くなりました。
電気自動車を開発して普及させることも該当しますし、消費電力の少ない家電製品に関しても同様です。
さらに、既存のものをうまく組み合わせることで、省エネを図るような取り組みに熱心な企業も見受けられます。
たとえば店舗などで用いている空調機が複数ある場合に、効率的に連携させることで消費電力を大きくカットできます。
言い換えると、何も考えずにやみくもに起動させているだけでは、電力を浪費することになってしまうのです。
2台の空調機を設置している場合、一方が暖かい空気を出して、もう片方がそれを冷やす空気を出すような事例もあります。
そういった無駄を見つけて省いていくような取り組みも、環境を守る重要な事業に他なりません。
空調の例でいうと、今後の温度変化を予測して暖め過ぎや冷やし過ぎを減らすことも当てはまります。
また、スーパーなどでであれば、夏場に空調とショーケースの冷気を関連づけて最適にするのも一つの手です。
このように、いろいろと視野を広げることによって、環境事業は大きな広がりを見せることになります。
2.資源を保護する環境事業の事例
また、建築業界においても独自の観点から環境を守る事業を行っている企業がたくさんあります。
金属や石材を主な材料とする方針から一転して、木材で建物を造るところが増えました。
加工に必要な火力が少ないですし軽いので運搬が楽です。
したがって、完成までにかかるエネルギーが少なくて済みます。
その結果、二酸化炭素の排出量も減らせるので温暖化を防ぐことにつながります。
さらに、木材には金属や石材みたいに音を響かせずに吸収しやすいという特性があるのもポイントです。
そのため、周囲の人々の生活環境の改善という意味でも大きな役割を果たしてくれます。
また、建物に積極的に遮光用の塗料を使用するようになった企業も少なくありません。
夏場の日差しを外壁でカットすることにより、室温が上昇していくのを防ぎやすくなります。
そうするとエアコンにかかる負担が少なくなるので、必然的に電力の使用量も減らせるというわけです。
塗料だけでなく、優れた断熱材を用いるケースも多くなっています。
いずれにせよヒートアイランドと呼ばれる状態を抑えるのに効果的です。
住宅をはじめとした建物は長期にわたって用いるのが一般的なので、最初にしっかりと省エネの仕組みを導入しておくことで高い効果を見込めるようになります。
初期投資がかかりますがランニングコストの節約によって回収することが可能です。
また、資源を保全する観点から環境事業を行っている企業も見受けられます。
森や林を増やすために木を植える活動を行っていますが、こちらは何十年にも及ぶ計画に沿って進めるのが大きな特徴です。
自然が失われるのは一瞬のことですが、それを元通りにするのには途方もない年月が必要となります。
そのため、企業にとっては見返りよりもコストのほうが大きくなってしまいがちです。
そもそも何十年も存続を確証されている企業など存在しません。
それでも地球とともにあり続けることを望んで、少しずつでも自然を回復させようと努めているのです。
3.廃棄物再利用の活動も大事な環境事業
木材は人間の生活に欠かせないものであり、安定的な供給を維持するためにも欠かせない活動といえます。
そのような取り組みを推進していくのは、一つの企業だけでは難しいというのが実情です。
行政を他の団体と協力しながら進めていこうとする動きが活発になってきました。
また、産業や生活の廃棄物を再利用していくという新東京グループに代表される環境事業も存在します。
単純に廃棄するだけでは環境にとってマイナスにしかなりません。
それを産業や生活の資源として使えれば、他の資源の使用量を低減できます。
具体的には燃料にしたり固形物の原料にしたりする方法があり、廃棄物の処理の意味合いもあって一石二鳥となっているのです。
このようなことを可能にするのは高度な技術が必要となります。
そういった技術の研究開発も環境を守る大事な事業に他なりません。
もちろん企業だけでなく、自治体も積極的に環境事業を取り組んでいます。
たとえば、災害で出た瓦礫などを回収する活動もその一つに数えられます。
民営化の話も出ていますが、水道事業のなかで行う水の浄化も自然にとって優しいものです。
このように、環境を良くしていく活動は、さまざまな立場の組織が取り組む事業となっています。
イメージアップのために取り組みを検討する企業も少なくありません。